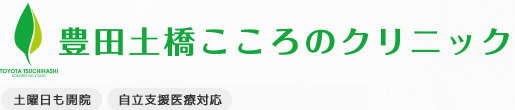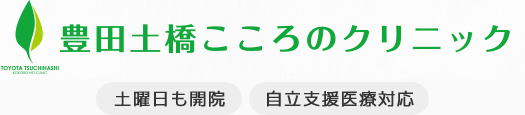- ホーム
- 医院ブログ
- その他の院長の興味がある事
- ChatGPTのハルシネーションはなぜ起こりますか?頻度は低下したのか?社会への問題点は?
ブログ
ChatGPTのハルシネーションはなぜ起こりますか?頻度は低下したのか?社会への問題点は?
<院長> 昔、ChatGPTで色々と質問していたときに、自信満々の答えの中に明らかに間違っている答えを見つけたことがあります。これをハルシネーションと呼ぶようです。これについてChat GPTに聞いてみました。
Q:ChatGPTのハルシネーションがなぜ起こるのか?頻度は低下したのか?社会への問題点は?
A:ChatGPT: ChatGPTのハルシネーション(幻覚)が起こる理由
ChatGPTを含む大規模言語モデル(LLM)は、基本的に「統計的なパターンに基づいて最も可能性の高い単語を予測する」仕組みで動作しています。そのため、次のような理由で事実とは異なる情報(ハルシネーション)を生成することがあります。
- 学習データの限界
- 訓練データに含まれる情報が不完全、不正確、または誤解されやすい場合、誤った情報を生成する可能性があります。
- 特に専門分野では、最新の知識や正確なデータが十分に含まれていないことがある。
- 確率的生成の特性
- LLMは「最も自然な文を作る」ことを目的としているため、情報の正確性を100%保証するものではない。
- 事実が分からない場合でも「それっぽい答え」を出すことがある。
- 文脈の誤解
- ユーザーの質問を誤解し、不適切な回答を生成することがある。
- 長い対話の中で、前の情報を適切に関連付けられないことがある。
- 新しい情報に対応できない
- 訓練データのカットオフ後に発生した出来事や、新しい研究成果については知らないため、誤った推測をする可能性がある。
ハルシネーションの頻度は低下したのか?
ChatGPTや他のLLMは、技術の進歩によりハルシネーションの頻度は低下していますが、完全には解決されていません。その理由と改善策には以下のようなものがあります。
改善された点
- ファクトチェックの強化
- 一部のモデルは外部のデータベースと照合し、リアルタイムで事実を確認できるようになっている。(例:ウェブ検索機能)
- 「この情報は確実に正しいか?」をチェックする仕組みが追加されている。
- 学習データの質の向上
- フィルタリング精度が向上し、誤った情報やバイアスの強いデータが減少。
- ユーザーのフィードバックを活用し、誤回答を修正する仕組みが強化されている。
- 自己検証・出典の表示
- 一部のモデルでは、出典を表示する機能が導入され、根拠のある情報提供が可能になっている。
- より高度なプロンプト処理
- ユーザーの意図をより正確に理解できるようになり、質問の誤解が減少。
まだ解決されていない課題
- 完全なファクトチェックが難しい → 外部データとリアルタイムで照合しない限り、誤情報を防ぐのは難しい。
- 高度な専門知識のハルシネーション → 専門分野(医療、法学、数学など)では依然として誤回答が出ることがある。
- 長い会話の中での誤り → 文脈の保持が完璧ではなく、誤った結論を出す場合がある。
社会への問題点
ハルシネーションは社会にさまざまな影響を与える可能性があります。
- 誤情報の拡散
- ChatGPTが間違った情報を提供すると、それを信じたユーザーがさらに拡散し、誤情報が広まる。
- 特に健康・医療・金融などの分野では、大きなリスクを伴う。
- フェイクニュースの増加
- AIが作った「もっともらしい嘘」が、フェイクニュースとして悪用される可能性がある。
- 悪意のあるユーザーが意図的に偽情報を作り出し、拡散する恐れがある。
- 法律・倫理の問題
- ハルシネーションによって名誉毀損や誤った法律情報を提供することがあり、責任の所在が問題になる。
- AIの発言の信頼性が問われるケースが増加。
- 教育や研究への影響
- 学生や研究者がAIの誤情報を信じてしまうと、学習や研究の質が低下する恐れがある。
- 「AIが言っているから正しい」という誤った認識が広がるリスク。
結論
ChatGPTのハルシネーションは技術の進歩により減少しつつあるが、依然として発生する問題であり、完全な解決には至っていません。特に、医療・法律・金融・歴史などの分野では、ユーザーが必ず出典を確認し、複数の情報源と照らし合わせることが重要です。今後の課題として、AIのリアルタイムファクトチェック機能の強化や、透明性の向上が求められます。
<院長> Chat GPTに聞いた時は、やはり専門家によるファクトチェックが必要ですね。
2025.03.13 | その他の院長の興味がある事,医院ブログ
医院ブログ
最近の投稿
カテゴリ
- ADHD 多動 不注意 衝動性
- 自閉スペクトラム症(ASD) 広汎性発達障害(PDD)
- DSM-5
- ヒトの遺伝と多様性に関して
- 論文紹介
- 院長の独り言
- 院長の著書一覧
- PTSD ASD
- その他の不安症
- パニック症 パニック障害
- 社交不安症 社交不安障害 社会不安障害 SAD
- うつ病 一般
- ご家族の方へ うつ病に関して
- マインドフルネス
- 中高年のうつ病
- 働く人のうつ病
- 女性のうつ病 不登校 子育て 受験 妊娠出産 月経困難 気分の波
- 復職 リワーク
- うつ病のすべての記事
- その他の良くある病気
- ストレス 適応障害 孤独
- 不安障害
- 不眠症(睡眠障害)
- こころの症状や病気
- その他の院長の興味がある事
- よく頂くお問い合わせへの回答
- クリニックからのお知らせ
- クリニックの特徴
- リクルート
- 交通アクセス
- 医学論文の読み方
- 医療費 窓口負担 書類
- 当院の基本理念
- 治療
- 開院前の様子
- 院長
- てんかん
- 体の病気
- 依存症
- 双極性障害 Bipolar disorder 1型 2型
- 痛み
- 発達障害
- 統合失調症
- 脳器質疾患
- 解離
- 認知症
- カウンセリング
- 認知行動療法(CBT)
- 心理療法
- 漢方薬